こんにちは。あおありです。
この記事ではアルバム「Xscape」発売10周年を記念し、印象的な収録曲
の制作背景やメッセージについて記載しています。
2014年にマイケルの未発表曲を収録した「Xscape(エスケイプ)」が発表されてから10年経ちました。
マイケルがこの世を去ったあとに制作されたため、アルバムの存在自体に賛否両論あります。
制作関係者たちにも、「今まで知らなかった曲を、自分たちが編集し公表して良いのだろうか?」という迷いがありました。
プロジェクトを主導したL.A.リードが最初に設定したルールは、「マイケルが最初から最後まで何度も歌った曲だけを使う」というもの。
自分の中でルールを決めたんだ。マイケルが最初から最後まで何度も歌った曲にしか関心を持たないと。なぜなら、マイケルがその曲を気に入ったか、それで分かるから。
マイケルが世界に聞いて欲しくないと思ってる曲を、我々が発表することは避けたかった。I made a rule for myself, I’m only interested in songs that Michael sang from top to bottom multiple times. Because then I would know that he loved the song.
L.A. Reid, Xscape Documentary
Because I didn’t want us to put out music that Michael didn’t want the world to hear
反対意見はあっても、未発表曲とは思えないクオリティーの名曲ぞろいであることは事実。
この記事では
こんな内容を記載しています🎵
Slave To The Rhythm

Slave To The Rhythmは、なんともマイケルっぽい曲。
ダークなムードのなか、強迫的に”Slave to the rhythm”というフレーズが繰り返されます。
家庭でも仕事でも支配的な男性に酷使される女性のストーリー。
しかし「Slave To The Rhythmって、マイケルのことじゃない?」と考えるマイケルファンは多いでしょう。
様々な想像をかき立てるこの曲を掘り下げます。
制作背景: Dangerousのアウトテイク
Slave To The Rhythmは1990年、L.A.リードとベイビーフェイスが作成したグルーブをベースに、マイケルが歌詞やメロディーなどを付けて作曲されました。
プロデューサーも驚くマイケルの熱意

共同制作したプロデューサーのL.A.リードは、マイケルのエネルギーに驚きました。
マイケルは休憩もなしに24回、最初から最後まで歌い続けたのだそう。
歌を1回録音して、悪いところを直すってもんじゃない。
違うんだ。マイケルはトイレにも行かず、水も飲まず、最初から最後まで通して24回歌った。「ちょっと待って」とも言わなかった。
彼は一曲歌ってから、「オッケー、もう一回流して。もっと良くできるから」といって最初から歌ったんだ。“it was not [record the vocal] once and fix the bad note. No, he sang the song from top to bottom twenty-four times without a bathroom break, without a water break, without a ‘Give me a moment.’ He would sing the song and say, ‘OK, give me another track, I can do it better,’ and he’d do it again.”
Vogel, Joseph. Man in the Music (p.220). Knopf Doubleday Publishing Group. Kindle 版.
マイケルの思い入れの強さがうかがえるエピソードです。
繰り返し候補に上がったが、選考されず
L.A.リードは諸事情あってDangerousのプロデューサーから外れました。
マイケルは後にタッグを組んだテディー・ライリーにこの曲のプロデュースを依頼。
しかしDangerousには収録されませんでした。
2001年に発表された”Invincible”、マイケルが亡くなった直後にリリースされた”Michael”の収録候補にも上がっていました。
搾取され、逃げられない女性の物語

Slave To The Rhythmの歌詞は、家庭でも職場でも支配的な男性のもとで働く女性のストーリーです。
奉仕することを「リズムに合わせてダンスする」と表現
彼女が働くこと、奉仕することを「ダンスする」と表現し、一日中ダンスする彼女は「リズムの奴隷」と暗喩されています。
謎その1: 愛のリズムとは?
女性の夫は彼女の働きに感謝せず、冷たい様子。
良好な関係とは考えにくく、彼女は「奴隷」として生きている。
しかし彼女は「愛のリズム」の奴隷と歌っています。
‘Cause she’s a slave to the rhythm
A slave to the rhythm of
A rhythm of loveなぜなら彼女はリズムの奴隷だから
愛のリズムの奴隷さ
この愛とはなんでしょうか?
どれも決め手に欠けており、謎めいています。
謎その2: 本当に逃げないのか?

支配から逃げられず、「鎖を壊せない」彼女。
しかしこの曲で一番盛り上がるパートは、彼女が家を抜け出し「自分自身のビートに合わせて」ダンスする場面です。
As she ran out the door
She danced through the night in fear of her life
She danced to a beat of her own
She let out a cry and swallowed the pride
She knew she was needed back home, home彼女が外に出た時
身の危険を感じながら夜通し踊った
彼女自身のビートに合わせて踊った
叫び声をあげ、プライドを飲み込んだ
分かっていた
家に戻らなければいけないことを
「逃げられない」状況とは裏腹に、逃避を予感させるフレーズがチラつく歌詞。
果たして彼女は本当に逃げられないのか?一生このままなのか?それとも…
謎を残したまま幕を閉じます。
マイケル本人を連想させるタイトル
Embed from Getty ImagesSlave To The Rhythmというワードを見て、「マイケルのことでは?」と考えたファンは多いでしょう。
マイケルは踊っているときの自分自身を「リズムの奴隷」と言いました。
マイケルは他の作品でも、自我の意識を超えて音楽に没頭する様子を、繰り返し説明しています。
また「Slave(奴隷)」という単語は歴史的、政治的に非常にセンシティブでもあります。
マイケルは作品の中に、迫害を受けてきた自らの祖先の歴史を刻み込んだのかもしれません。
僕はリズムの奴隷なんだ
マイケルは1993年にテレビ放送されたインタビューで、「僕はリズムの奴隷だ」と答えています。
司会のオプラ・ウィンフリーに「世の中の母親たちに質問しろといわれてるの。なぜあなたはパフォーマンス中に股間をつかむの?」と質問された時のことでした。
踊るときは、曲、音、伴奏を解釈しているんだ。つまり激しいベースや、チェロとか、弦楽器の音があれば、それが奏でる情感そのものに自分がなる。だから、僕が踊ってバン!とやって自分自身を掴んだとしても、音楽がそうさせてるだけだよ。
僕が下に手を伸ばして掴みたくてたまらないわけじゃない。触っていい場所じゃないよね…なんてことも考えない。ただ、それが起こるだけ。
時々映像を見返して、びっくりすることもある。僕はこんなことしたの?て。
だから僕はリズムの奴隷なんだ。
When you’re dancing, you know you are just interpreting the music and the sounds and the accompaniment
if there’s a driving base, if there’s a cello, if there’s a string, you become the emotion of what that sound is, so if I’m doing a movement and I go bam and I grab myself it’s… it’s the music that compels me to do it, it’s not saying that I’m dying to grab down there and it’s not in a great place you don’t think about it, it just happens, sometimes I’ll look back at the footage and I go … and I go did I do that, so I’m a slave to the rhythm
“Slave”はマイケルの創造性に不可欠なキーワード
Embed from Getty Images音楽に入り込み、憑依されたように踊るスタイルは、マイケルのパフォーマンスの要と言っても過言ではありません。
マイケルはこの様を「リズムの奴隷になる」と呼びました。
Dangerous発表と同時期に出版されたマイケルの詩集「Dancing The Dream」にも、リズムの奴隷になる過程が詳しく描かれています。
On many an occasion when I’m dancing, I’ve felt touched by something sacred.
In those moments, I’ve felt my spirit soar and become one with everything that exists.
I become the stars and the moon.
I become the lover and the beloved.
I become the singer and the song.
I become the knower and the known
I keep on dancing and then, it is the eternal dance of creation.
The creator and creation merge into one wholeness of joy.僕は踊っている最中、何度も神聖な何かに触れられる感じがした
マイケルジャクソン, dancing the dream
そんな時、僕の魂が舞い上がり、存在しているものすべてになった気がした
僕は星になり月になる
愛する人になり、愛される人になる
歌手になり、歌になる
知る人になり、知られる人になる
僕は踊り続け、それは永遠の創作だ
創造者と創造は一つの完全な喜びに溶け込む
禅、マインドフルネス、ヨガなど、東洋で生まれた概念とも共通する概念です。
解釈1: 黒人の歴史背景

「奴隷(Slave)」という言葉は、アメリカ人にとって非常にセンシティブです。
アフリカ系アメリカ人の祖先の多くは、奴隷としてアフリカから連行された人々。
奴隷制度が廃止された後も、長い間差別や不当な扱いに苦しんできました。
人種差別の壁に何度もぶち当たってきたマイケル。
彼が”Slave”と口にするとき、迫害を受けながらも、必死で逃げようとしてきた仲間たちの歴史をひそかに刻んだのかもしれません。
解釈2: 実質的な支配を受ける人々
この歌で語られる女性のように、法律上は対等であっても実質的に支配され、「依存と支配」にしばられた人間関係に苦しむ人々は少なくありません。
なかには「共依存」と言われるように、双方に原因があって複雑にからみあっているケースも。
人間だけでなく、カルト宗教、アルコール、薬物、ギャンブルや買い物などに依存した人は、実質的に自由を失った「奴隷」とも言えます。
支配や依存の沼におちいった結果、多くの人が本来の健康的な人生から外れてしまう深刻な社会問題を風刺しているかもしれません。
解釈3: 自由とは言えないマイケルの生活
子供の頃から練習づけ、働き詰めのマイケル。常にメディアや人々に追いかけられて、自由とは言えない毎日。
そんな憂うつをこの歌に発散したかもしれません。

「レコード会社の奴隷でなく、あくまでリズムの奴隷なんだ」というプライドを示したのかも…
Do You Know Where Your Children Are

Do You Know Where Your Children Areは、アメリカで夜間に繰り返しテレビ放送された注意喚起から着想を得た曲です。
マイケルが長年訴えてきた「もっと子どもたちに注目して!」というメッセージが読み取れます。
制作背景: Badのアウトテイク
1986年、Bad製作時にマイケルがビル・ボットレル、マット・フォージャーと制作。
シンプルでインパクトのあるメロディーラインにビル・ボットレルらしさを感じます。
Badの選考から外れ、Dangerousの候補曲にもなりましたが、選考に至りませんでした。
テレビ放送から着想を得た
アメリカでは、子どもたちが夜中に街をふらついて危険な目に合い、その両親たちは子供に無関心…というケースが社会問題となっていました。
子供たちを守るため、1960年代から80年代にかけて夜10時と11時のニュース時に
“It’s 10 PM. Do you know where your children are?”
(現在夜の10時です。あなたの子どもたちがどこにいるか、知っていますか?)
と繰り返し放送されました。
このフレーズを流用した曲が”Do You Know Where Your Children Are”です。

マイケルは最終警告の12時バージョンを作ったのかな?
マイケルのメッセージ: もっと子どもたちに注目して!

この曲のインスピレーションについて、マイケルはこんなメモを残しています。
崩壊した家族で育てられた子どもたちの歌だ。
マイケルジャクソン公式サイト記事より
父親が酔っ払って家に帰り、母親が家を出て売春し、子どもたちは家から逃げ出す。
そしてレイプ、売春の犠牲となり。狩人たちは捕まえられる。
“Song is about kids being raised in a broken family where the father comes home drunk and the mother is out prostituting and the kids run away from home and become victims of rape, prostitution, and the hunter becomes the hunted.”
マイケルは他の作品でも、「過酷な環境で育てられる子どもたち」「虐待やネグレクトの被害にあう子どもたち」に言及しています。
Thriller収録曲”Wanna Be Startin’ Somethin'”の一節では、親になる準備ができていない人達(多くは10代の若者)の妊娠・出産をほのめかしています。
If you can’t feed your baby
Then don’t have your baby
And Don’t think maybe
If you can’t feed your baby赤ちゃんを食べさせてあげられないなら
Wanna Be Startin’ Somethin’の歌詞より
子供をもっちゃいけない
多分大丈夫なんて考えるな
食べさせてあげられないのなら
Dangerous収録曲”Why You Wanna Trip On Me”では、子どもたちの学校教育が抱える問題を指摘。
But there’s a bigger problem that’s much more in demand
Why You Wanna Trip On Meの歌詞より
You’ve got world hunger, not enough to eat
So there’s really no time to be trippin’ on me
You’ve got school teachers who don’t wanna teach
You’ve got grown people who can’t write or read
世の中にはさらに差し迫ったもっと大きな問題がある
世界の飢餓 食べ物が足りないんだ
だから僕にかまっている時間なんてない
教えたくない学校の先生がいる
読み書きできない大人がいる
HIStoryの収録曲”Little Susie”は、家族を失い、孤独のなか幼くして亡くなってしまった少女を描きます。
Neglection can kill
Like a knife in your soul
Oh, it will
Little Susie fought so hard to liveネグレクトは人を死に至らせる
Little Susieの歌詞より
魂を傷つけるナイフのように
あぁ そうさ
幼いスージーは必死に生きようとした
Invincible収録曲の”The Lost Children”も同様に、十分な注目を受けていない子どもたちをテーマにしています。
Home with their fathers
Snug close and warm, loving their mothers
I see the door simply wide open
But no one can find thee父親のいる家
The Lost Childrenの歌詞より
安全で、あたたかくてほっとする
母親を愛している
ドアははっきり大きく開いているのに
だれも君を見つけられない
A Place With No Name

喜びあふれる別世界を表現した”A Place With No Name”
実は別アーティストの曲をリメイクした作品でした。
元になった曲”A Horse With No Name”とマイケルが作成した、”A Place With No Name”、そしてXscape発表用にプロデュースされた”A Place With No Name”を比較します。
“A Horse With No Name”のカバー
元になった曲は1971年にAmericaというバンドが発表した“A Horse With No Name”
マイケルは1998年、メロディーラインをそのまま残し、歌詞を大幅に変えた”A Place With Without No Name”をドクター・フリーズと共に制作しました。
原曲は広大な砂漠、MJは華やかな理想郷を描く

元になった”A Horse With No Name”は、どこまでも広がる砂漠と自然をイメージさせます。
一方マイケルのA Place With No Nameでは、人々の笑顔や動物、美しい自然など、より彩り豊かな世界を表現しています。
「日常の喧騒から離れた美しい世界」を描いている点は同じです。
素朴なオリジナル版、ダンサブルなリメイク版
マイケルたちが制作したオリジナル版は、”A Horse With No Name”の素朴なサウンドを継承しています。
アコギギターのベースに、ドラムを付け足している感じ。
一方Xscapeで制作された”A Place With No Name”はテイストが一変し、ゴージャスでダンサブルなサウンドです。
まとめ
Xscape収録曲のなかから
上記の3曲について、制作背景やメッセージなどを掘り下げました。
ここまで読んでくださり、ありがとうございます!
この記事を読んで、マイケルの作品がより楽しめるようになったら幸いです。
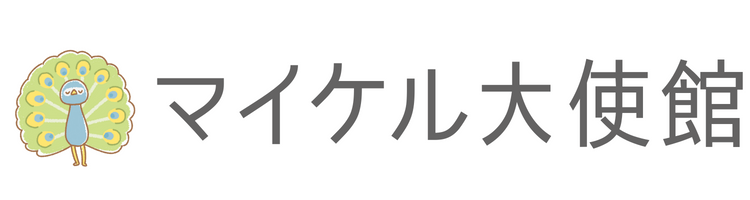



コメント
マイケルの「遊びの代償に子供を巻き込まない」でという永遠のテーマ。子供の幸せを常に願い、自分のカリスマ性を武器に訴え続けたことを多くの人にもっともっと知ってもらいたい。オックスフォード大学の講義のなかでマイケルの子供の憲章には「愛していると言われる権利」「寝る前に絵本を読んでもらえる権利」と子ども目線で訴えていました。でもあれは子ども目線ではなく子供時代のマイケルが言っていたのかも。ならばSlave To The Rhythmは意外にもマイケルのことを描いているのではなく、冷めた夫婦の間にいる子供を憂いて、「おかあさん、つらいかもしれないけどおうちに帰ってあげて」と言っているような気がしてきました。歌詞のかっこよさにまったく歌詞の意味を知らず聴いいました。解説とても楽しく読ませていただきました。ありがとうございます。
Luxさん、コメントありがとうございます!
マイケルは常に子どもたちのためにメッセージを送り続けてきましたね。
確かに、Slave To The Rhythmも、子ども目線に立つと違う側面が見えます。
新しい視点🤩